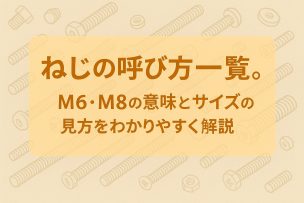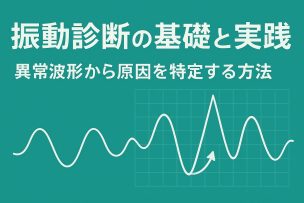
モータやポンプなどの回転機械では、わずかな振動変化がトラブルの前兆となることがあります。
この記事では、振動計を活用した「設備診断」の考え方と、波形から異常を読み取る基本ポイントを解説します。
振動診断とは?(基礎知識)
振動診断とは、設備の振動データを測定・解析し、異常の有無や劣化状態を評価する手法です。
主に回転機械(モータ、ポンプ、ファン、ブロワ、減速機など)の状態監視に用いられ、予知保全の中心的な役割を担います。
- 運転中の振動を定期的に測定
- 過去データとの比較で傾向を分析
- 異常の兆候(波形・周波数)を検出
このように、単なる「測定」ではなく、データから原因を「診断」するのがポイントです。
振動の基本パラメータ
振動診断では、以下の3つの指標を組み合わせて評価します。
| 項目 | 単位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 振動加速度(Acceleration) | m/s² | 高周波域に敏感。ベアリングの損傷などの検出に有効。 |
| 振動速度(Velocity) | mm/s | 全体的な振動強さを評価。ISO10816の判定基準に使用。 |
| 振動変位(Displacement) | μm | 低周波域のゆらぎを捉える。アンバランスなどに有効。 |
異常波形からわかる主なトラブル
振動診断では、周波数成分のパターンから故障原因を推定します。
| 異常の種類 | 主な特徴 | 波形・周波数の傾向 |
|---|---|---|
| アンバランス | 回転軸の偏り。高速回転で振動が増大。 | 回転数と同じ1×成分が顕著。 |
| ミスアライメント | 軸ずれや結合部の芯出し不良。 | 1×+2×成分が混在。 |
| 軸受損傷 | ベアリングの摩耗や欠損。 | 高周波ノイズ成分が増加。 |
| ゆるみ・がた | ボルトの緩み、ベース固定不良。 | ランダムノイズや広帯域振動。 |
| 電気的トラブル | モータのコイル不良や磁気不均衡。 | 極数倍成分(2×, 3×)が出現。 |
測定から診断までの流れ
- 対象機械の運転状態を確認(定常運転時に測定)
- 振動計または加速度センサを取り付け
- 複数箇所のデータを取得(水平・垂直・軸方向)
- 波形・スペクトル分析で異常傾向を確認
- 前回データや基準値との比較
特に、ISO10816(機械の振動評価規格)を基準に評価することで、異常の定量判断が可能になります。
データ管理とトレンド分析
診断の精度を高めるには、定期測定データを蓄積し、時間軸で傾向を把握することが重要です。
近年では、無線センサやクラウド管理システムを用いて、リアルタイムに状態を監視するケースも増えています。
- 異常の早期検知(閾値超過の自動通知)
- 波形データの自動解析(AI診断)
- 報告書・グラフ出力機能
代表的な振動診断ツール
代表的なメーカーと特徴を紹介します。
| メーカー | 主な機種・特徴 |
|---|---|
| リオン(RION) | ポータブル振動計、FFT分析機能付きモデルを展開。 |
| 小野測器(ONO SOKKI) | 産業用振動解析装置。回転同期測定にも対応。 |
| キーエンス(KEYENCE) | 非接触型変位センサを用いた診断システム。 |
| IMV株式会社 | 常設型モニタリングシステム。クラウド監視対応。 |
まとめ
振動診断は、回転機械の健全性を数値で把握する有効な手段です。
異常波形の特徴を理解し、定期的にデータを比較・蓄積することで、突発的な設備停止を防ぐことができます。