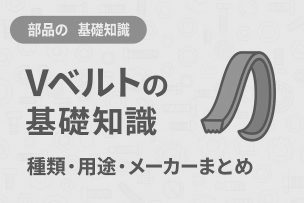電気設備の安全運用には、絶縁劣化の早期発見が欠かせません。
従来はメガーによる定期測定が中心でしたが、近年は絶縁監視リレー(IMD)や漏電監視装置(ELD)によるリアルタイム監視が普及しています。
この記事では、それらの原理・設置・診断運用のポイントを整理します。
絶縁監視リレー(IMD)とは?
絶縁監視リレー(Insulation Monitoring Device)は、活線状態でも接地抵抗を監視し、絶縁低下を自動検出する装置です。
主に非接地系統(IT系統)で使用され、医療施設や制御盤、変電盤などで電源を切らずに状態把握が可能です。
- 電圧印加方式や電流検出方式で絶縁抵抗を常時監視
- 異常値を検知すると警報リレーを出力
- デジタル通信対応機種では記録・解析・遠隔通知も可能
監視原理(例:電流検出方式)
中性点非接地回路に微小な信号電流を流し、帰路電流の変化から絶縁抵抗値を算出します。
「健全時は微弱電流」「劣化時はリーク増加」となるため、リアルタイムで傾向監視ができます。
漏電監視装置(ELD)との違い
| 分類 | 主用途 | 監視原理 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 絶縁監視リレー(IMD) | 非接地系統の絶縁監視 | 微弱電流検出/信号電圧印加 | 電源切断不要・常時測定が可能 |
| 漏電監視装置(ELD) | 接地系統の漏電監視 | 零相電流変流器(ZCT)で漏電電流を検出 | 接地系統向け・負荷ごとの分離監視が容易 |
IMDは「絶縁抵抗の健全性」監視、ELDは「実際の漏電発生」監視と覚えると明確です。
主な診断パラメータと閾値設定
| 項目 | 監視対象 | 代表的な設定値 | アラーム対応 |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗(Riso) | 対地抵抗値 | 0.5〜2 MΩ以下で警報(設備種別により調整) | 配線・機器単位で切り分け確認 |
| 漏電電流(Ileak) | ZCT二次電流 | 10〜30 mA(警報)/100 mA以上(遮断) | 相別・回路別トレンドを記録 |
| 警報遅延時間 | 突発ノイズ対策 | 0.5〜3秒 | 誤報防止設定(ノイズフィルタ併用) |
診断・管理の基本フロー
- 盤ごとにIMDまたはELDを設置(非接地/接地系統で区別)
- 閾値と警報出力先を設定(音響・表示灯・PLC入力など)
- 測定ログを週次・月次で確認(トレンド監視)
- 劣化傾向を発見したら絶縁抵抗計で再測定
- 原因回路の切り分け・ケーブル補修・再試験
クラウド・PLC連携による傾向監視
最新の監視リレーは通信機能を備え、複数盤のデータを統合監視できます。
- Modbus/TCP, RS-485通信で値をPLCに集約
- クラウド連携でメール通知・ダッシュボード化
- 複数回路のRiso・Ileakを一元管理
代表的なメーカー・装置例
| メーカー | 主な製品・特徴 |
|---|---|
| 三菱電機 | ELD形漏電監視リレー。配電盤組込型で多回路同時監視。 |
| 日東工業 | 漏電監視ユニット+ZCT内蔵。分電盤向け。 |
| IDEC | 非接地系統用絶縁監視リレー(IMD形)。LED表示+通信対応。 |
| 富士電機 | 医療設備・UPS用高感度IMD。長距離通信対応。 |
| 日置電機(HIOKI) | ポータブル型リーク電流計。点検・校正用途に最適。 |
運用上のポイント
- 誤警報対策:ノイズフィルタ・遅延設定・アラーム履歴保持
- 感度調整:盤単位・回路別の電流閾値を見直し
- 校正周期:年1回以上(ZCT・IMDとも)
- 復帰条件:自動復帰/手動復帰を選定し、復旧操作手順を標準化
まとめ
絶縁監視リレーや漏電監視装置は、「メガー測定と現場感覚の間を埋める常時監視ツール」です。
定期測定に加え、リアルタイム監視を組み合わせることで、電気設備の安全性と稼働率を飛躍的に高められます。