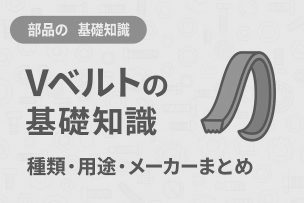モータ電流信号を周波数解析し、回転機の機械・電気的異常を非侵襲に検出する手法がMCSA(Motor Current Signature Analysis)です。
振動計が設置できない環境や、配電盤側から簡易に監視したいケースで威力を発揮します。
MCSAとは?(基礎知識)
MCSAは、モータの相電流をクランプで非接触取得し、FFT(周波数解析)で特徴成分を抽出して故障モードを推定する診断手法です。
機械系(軸受・アンバランス)と電気系(ロータ欠陥・磁気不均衡・巻線短絡)に横断的に感度を持ちます。
- 非侵襲:配電盤側で測れる(配線改造不要)
- 常時監視が容易:CT/クランプ+ゲートウェイで連続ログ
- 振動・温度と併用することで判定精度が向上
検出できる主な異常とサイン
| 想定故障 | 電流スペクトルの特徴 | 補足診断 |
|---|---|---|
| ロータ欠陥(折損バー等) | 電源基本波 fs 周辺のサイドバンド(fs±2fslip など)が増大 | 回転数・負荷変動と相関を確認 |
| アンバランス/ミスアライメント | 回転基本成分に同期した側帯域の上昇 | 振動(1×/2×)との照合で確証度UP |
| 軸受劣化 | 高周波側の広帯域ノイズや特定倍音の増大 | 温度上昇・グリス状態と合わせて評価 |
| 巻線短絡・磁気不均衡 | 奇数高調波の偏り、相間の不整合 | 相電流のバランス/位相差を確認 |
| インバータ異常(駆動系) | PWMキャリア付近の成分やリップル異常 | DCリンクリプル計測で裏取り |
測定〜診断の基本フロー
- 計測点の定義:配電盤内の相電流(U/V/W)にクランプCTを装着
- サンプリング設定:基本波50/60Hzと高調波が十分入る周波数帯・分解能でFFT
- 運転条件の固定:負荷率・回転数・温度などを記録(再現性確保)
- スペクトル解析:基本波・側帯域・高調波・広帯域ノイズを評価
- 多元照合:振動・温度・赤外結果と突き合わせて故障モードを特定
判定のコツ(誤検知を避ける)
- 負荷依存性:ロータ欠陥のサイドバンドは負荷で変化するため、複数負荷点で比較
- 電源品質:電源側の高調波・瞬停による影響を切り分ける
- キャリブレーション:CTの位相ずれやゲインを校正、相間バランスの前提を整える
常時監視(オンライン化)のポイント
- クランプCT+データロガー(またはゲートウェイ)で常設化
- 閾値:側帯域レベル・高調波THD・相バランス指標にしきい値
- イベント連携:閾値超過→メール/Teams通知→是正オーダ自動発行
振動・温度とMCSAの役割分担
| 手法 | 得意分野 | 制約/弱み |
|---|---|---|
| MCSA | 非侵襲・配電盤側から横断監視 | 低速/超低振幅の機械異常は埋もれることがある |
| 振動 | 機械系の直接検知(1×/2×/BPFO等) | センサ設置やスペースの制約 |
| 温度/赤外 | 発熱の可視化・安全なリモート確認 | 初期段階の異常は温度差が出にくい |
代表的な構成例(機器選定のヒント)
- 計測:クランプCT(適正レンジ/帯域)+FFT解析対応ロガー
- 同期:回転同期(タコ)入力があると原因特定が早い
- クラウド:ダッシュボードで側帯域トレンドとイベント履歴を可視化
導入・運用チェックリスト
- 相別の電流・位相・高調波THDを月次でトラッキング
- 負荷ステップ(低/中/高)での基準スペクトルをライブラリ化
- 振動・温度のRAG判定とアラート種別を統一(誤報低減)
まとめ
MCSAは、配電盤側から非侵襲で回転機の健全性を見張れる強力な診断手法です。
振動・温度の結果と突き合わせることで誤検知を避け、常時監視とアラート運用を組み合わせれば、突発停止のリスクを効率的に下げられます。