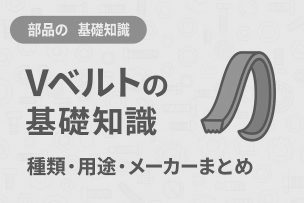工場や現場の安全を確保するためには、ルールや設備だけでなく、作業者一人ひとりの意識が欠かせません。
その基盤となるのが「5S活動」と「KY(危険予知)活動」です。
本記事では、労働災害を防ぐための現場改善の基本である5SとKYの進め方をわかりやすく解説します。
5S活動とは?
5Sとは、職場の秩序と安全を保つための基本的な活動で、次の5つの頭文字を取ったものです。
| 要素 | 意味 | 目的 |
|---|---|---|
| 整理(Seiri) | 不要な物を取り除く | ムダ・危険の排除 |
| 整頓(Seiton) | 使う物を使いやすく配置する | 探す手間の削減・作業効率化 |
| 清掃(Seisou) | 常にきれいに保つ | 異常の早期発見・故障防止 |
| 清潔(Seiketsu) | 整理・整頓・清掃の維持 | 職場環境の安定・衛生の確保 |
| しつけ(Shitsuke) | ルールを守る習慣づけ | 安全意識の定着・文化形成 |
5Sが安全に直結する理由
- 整理されていない現場は、転倒・衝突・感電などのリスクが高い
- 整頓された職場では、異常や危険が「見える化」されやすい
- 清掃により、漏れ・破損・摩耗などの異常を早期発見できる
KY活動とは?
KYとは「危険予知(Kiken Yochi)」の略で、作業前に潜む危険を予測し、事故を未然に防ぐ取り組みです。
全員で意見を出し合い、「どんな危険があるか」「どう対策するか」を共有することが目的です。
KY活動の4ステップ
- 危険の発見: 作業内容をもとに、想定される危険を洗い出す
- 危険ポイントの抽出: 特に重大なリスクを特定する
- 対策の検討: 手順・装備・環境の見直しで危険を低減
- 実施・振り返り: 対策の実行と効果確認を行う
KY活動の効果
- 安全意識の向上とチーム内コミュニケーションの促進
- ヒューマンエラーの防止
- 作業の危険源の「見える化」
5S・KY活動の具体的な実践例
現場改善の事例
- 通路に工具や資材を放置せず、定位置管理を徹底
- 作業前に「本日の危険ポイント」をホワイトボードに記入
- 点検・整備作業では「指差呼称」を導入
- KY結果を日報やチェックリストに記録して共有
管理側の取り組み
- 月1回の5Sパトロール・KYミーティングの開催
- 優良事例を社内掲示や朝礼で共有
- 安全教育・改善提案制度と連動させる
5S・KY活動を定着させるコツ
- 「安全は人任せにしない」意識を全員に浸透させる
- 活動を評価制度や表彰制度に組み込む
- 小さな改善でもすぐに反映・見える化する
- 5SとKYを分けず、日常業務の一部にする
おすすめの安全管理グッズ
Q&A
Q. 5SとKYはどちらを優先すべき?
A. 両者は補完関係にあります。5Sで安全な環境を整え、KYでその中の潜在リスクを洗い出すことで、安全が強化されます。
Q. KY活動は毎回必要?
A. はい。毎日の作業内容や天候・人員の変化によって危険は変化します。短時間でも継続が重要です。
Q. 5S活動を継続するコツは?
A. 点数制度や写真掲示など「見える化」で成果を共有するとモチベーションが維持できます。