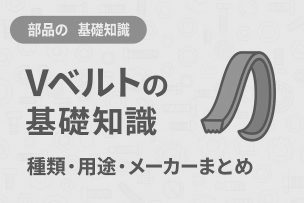工場や作業現場で労働災害を防ぐためには、リスクアセスメント(危険性・有害性の特定と評価)が欠かせません。
本記事では、リスクアセスメントの目的、実施手順、評価方法、改善の流れをわかりやすく解説します。
リスクアセスメントとは
リスクアセスメント(Risk Assessment)とは、作業や設備に潜む危険性・有害性をあらかじめ洗い出し、発生の可能性と被害の大きさを評価して、優先的に対策を講じるための手法です。
法令上の位置づけ
- 労働安全衛生法 第28条の2: 事業者にリスクアセスメントの実施努力義務を課す
- 労働安全衛生規則 第5条: 危険有害要因の特定と低減対策を明文化
- 厚生労働省指針(平成18年): 実施手順・記録・教育のガイドラインを示す
リスクアセスメントの目的
- 労働災害・設備事故の未然防止
- 安全対策の優先順位づけと合理化
- 法令遵守(労安法・化学物質管理など)
- 安全文化の定着と現場意識の向上
実施手順(5ステップ)
- 危険源(ハザード)の特定: 作業・設備・物質・動作の中から危険要因を抽出
- リスクの見積り: 「発生頻度 × 被害の大きさ」でリスクレベルを定量化
- リスクの評価: 許容できるかどうかを判断し、優先順位を決定
- リスク低減対策の検討: 排除・代替・隔離・保護具・教育などを実施
- 記録・見直し: 結果を文書化し、定期的に再評価
リスクの見積り方法
| 評価項目 | 区分 | 例 |
|---|---|---|
| 発生頻度(F) | 1:まれ 2:時々 3:頻繁 | 接触・作業回数など |
| 被害の大きさ(S) | 1:軽傷 2:中程度 3:重篤・死亡 | 想定される最大被害 |
| リスクレベル(R) | R=F×S | 数値が高いほど優先的に対策 |
例:グラインダー使用作業のリスク評価
| 危険源 | リスク内容 | F | S | R | 対策例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 砥石の破損 | 飛散による負傷 | 2 | 3 | 6 | 防護カバー設置・保護面着用 |
| 電源コード損傷 | 感電事故 | 1 | 3 | 3 | 定期点検・絶縁検査 |
リスク低減の基本原則(Hierarchy of Controls)
- 排除(Elimination): 危険作業をなくす
- 代替(Substitution): より安全な方法や物質に置き換える
- 工学的対策(Engineering Controls): 安全装置・フェンスなどで隔離
- 管理的対策(Administrative Controls): 作業手順・教育・表示
- 保護具(PPE): 最後の手段として個人防護具を使用
記録・報告書の作成例
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 対象作業 | プレス機の金型交換作業 |
| 危険源 | 手の挟まれ・落下物 |
| リスク評価 | F=2, S=3, R=6 |
| 対策内容 | インターロック導入・安全教育実施 |
| 評価者 | 安全管理者・職長・現場代表 |
主要支援ツール・システム
厚生労働省 リスクアセスメント支援シート
無料で利用できる公式テンプレート。業種別の危険要因リスト付き。
Safety Meister
クラウド上でリスク評価・是正履歴・改善進捗を一元管理できるツール。
ミスミ「Factory Manager」
設備点検・リスク評価・保守履歴をまとめて管理可能な現場向けシステム。
中災防(中央労働災害防止協会)
リスクアセスメント教育・チェックリスト教材を提供。
おすすめのリスクアセスメント教材を探す
Q&A
Q. リスクアセスメントは誰が実施すべき?
A. 原則として安全管理者または職長・作業責任者が中心となり、作業者を含めたチームで行うのが望ましいです。
Q. 実施頻度はどのくらい?
A. 新設備導入時や作業変更時、年1回以上の定期見直しが推奨されます。
Q. 結果はどのように活用しますか?
A. 教育資料や作業標準書、安全対策会議などに反映し、PDCAサイクルの中で改善を継続します。