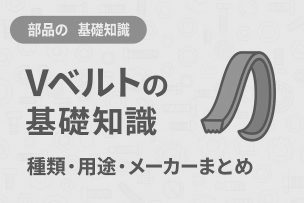リスクアセスメントを実施した後は、結果を明確に記録し、関係者と共有することが重要です。
本記事では、リスクアセスメント報告書の書き方、構成例、記入のポイント、保存・活用方法を解説します。
リスクアセスメント報告書の目的
- 危険源の特定結果とリスク評価の内容を明確に残す
- 改善策を関係部署・作業者と共有する
- 是正措置の進捗を管理・確認する
- 労働基準監督署や社内監査に対応できる記録を保持する
報告書の基本構成
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| ① 対象作業・設備 | 作業名、設備名称、実施日、実施場所 |
| ② 危険源の特定 | 作業動作・機械要素・化学物質などから抽出 |
| ③ リスクの評価 | 発生頻度(F)× 被害の大きさ(S)= リスクレベル(R) |
| ④ 対策の検討・実施 | 排除・代替・隔離・管理・保護具など |
| ⑤ 実施後の評価 | 残留リスクの再評価 |
| ⑥ 評価者情報 | 安全管理者、職長、関係部署責任者など |
テンプレート例
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 対象作業 | プレス機金型交換作業 |
| 危険源 | 手の挟まれ、落下物 |
| リスク評価(F×S) | 2×3=6(高リスク) |
| 対策内容 | 安全カバー設置、教育実施、インターロック導入 |
| 再評価 | 1×2=2(低リスク) |
| 評価者 | 安全管理者:山田 職長:鈴木 |
作成のポイント
- 数値化: リスクを定性的ではなく「F×S」で数値化
- 改善策の優先順位: リスク値の高い項目から対策を実施
- エビデンス添付: 写真・図面・SDSなどの根拠資料を添付
- 再評価の明記: 対策後のリスク値を記録し、効果を確認
- レビュー履歴: 年次見直しや定期再評価を明記
報告書の共有・保存方法
- クラウド管理: Google Drive・Dropbox・SharePointなどで共有
- バージョン管理: 改訂日・改訂者を明確にして履歴管理
- アクセス権設定: 編集権限を安全管理者・責任者に限定
- バックアップ: 定期的なデータ保存と印刷保管を併用
- 教育連携: 新人教育・KYT資料として再利用
主要支援ツール・テンプレート
厚生労働省 リスクアセスメント支援シート
業種別のチェック項目付きExcel形式テンプレートを無償公開。
Safety Meister
報告書フォーマットの自動生成、改善進捗の可視化機能を搭載。
現場PAD(kintone連携)
写真・音声入力対応の現場用報告アプリ。スマホ・タブレットから記録可能。
Googleスプレッドシート
共同編集・クラウド共有に適した無料ツール。チェックリスト管理に最適。
おすすめの報告書テンプレート・管理用品を探す
Q&A
Q. 報告書は誰が作成・承認すべき?
A. 原則として、安全管理者や職長が作成し、部門長・安全衛生委員会が承認します。
Q. 書式は自社で自由に作ってもよい?
A. 自社フォーマットでも問題ありませんが、評価方法や項目は厚労省指針に準拠させましょう。
Q. 保存期間の目安は?
A. 少なくとも3年間以上の保存が推奨されます。重大災害関連は5年以上保管します。