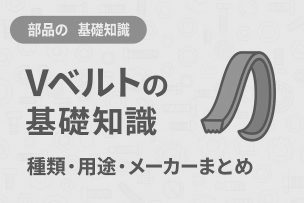予知保全(Predictive Maintenance)は、設備に取り付けたセンサで振動・温度・電流などの状態を常時監視し、故障の予兆を早期に検出して対策する手法です。
従来の「壊れてから直す(事後保全)」や「定期交換(予防保全)」に比べ、設備停止リスクと保全コストを大幅に低減できるため、多くの工場で導入が進んでいます。
この記事では、予知保全の仕組み、監視項目、具体的な診断方法、導入メリットを初心者向けにまとめて解説します。
予知保全とは?
予知保全(PdM:Predictive Maintenance)は、設備の状態を監視し、故障しそうなタイミングを予測してメンテナンスを行う保全方式です。
3つの保全方式の違いは以下の通りです。
| 保全方式 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 事後保全 | 壊れたら直す | 初期コストが低い | 突発停止・重大故障リスク |
| 予防保全 | 時間・回数で定期交換 | 安定稼働 | 早期交換が発生しやすい |
| 予知保全 | 状態監視で予兆検出 | 停止を最小化・寿命最大化 | センサ・システム導入が必要 |
予知保全でよく使われる監視項目
予知保全では、設備の状態変化を捉えるために「振動」「温度」「電流」を中心としたデータを監視します。
① 振動監視(Vibration Monitoring)
回転機械(モーター・ポンプ・ファン)では、異常の多くが振動として現れるため最も重視される指標です。
検出できる異常例:
- 軸受(ベアリング)損傷
- アンバランス・芯ズレ
- 軸の摩耗・ギヤの欠け
- 共振・緩み
② 温度監視(Temperature Monitoring)
温度は設備の健康状態を表す最も基本的な指標で、以下の異常を検出します。
- 軸受の発熱(潤滑不良)
- モーター巻線の過熱
- 配電盤内部の温度上昇
- 電装品の劣化
赤外線サーモグラフィは設備全体の温度分布を可視化する際に有効です。
③ 電流監視(Current Monitoring)
モーターや加熱機器では、電流値の変化が負荷状態や異常の初期兆候を示します。
検出できる異常例:
- 負荷の増加(ポンプ詰まり・ベルト緩み)
- 絶縁低下による電流上昇
- 電源異常・三相不平衡
予知保全に使用されるセンサ・測定機器
- 振動センサ(加速度・速度・変位)
- 温度センサ(熱電対・PT100・表面温度センサ)
- 電流センサ(クランプ式・変流器 CT・電力センサ)
- 無線センサ(IoTセンサ)
- データロガー・計測クラウド
- 赤外線サーモグラフィ
これらを組み合わせることで「いつ・どこで・どんな異常が発生しそうか」を判断できます。
予知保全の導入メリット
- 突発停止の大幅削減(生産停止による損失回避)
- 設備寿命の延長(劣化を早期に把握)
- 部品交換の最適化(無駄な予防交換を削減)
- 省エネ効果(負荷上昇を早期に検知)
- 安全性向上(軸受焼損や過熱事故を防止)
予知保全の導入ステップ
1. 重要設備(クリティカルマシン)の選定
モーター・ポンプ・コンプレッサなど停止時の影響が大きい設備を優先。
2. 監視項目の選定
- 回転機械 → 振動、電流、温度
- 電装品 → 温度、電流
- 油圧・空圧 → 圧力、流量、電流
3. センサ・計測機器の設置
無線センサを使えば既設設備へ後付けしやすい。
4. データ収集と傾向監視
クラウド・データロガー・IoTゲートウェイを活用。
5. 異常判定とアラート設定
AI診断・しきい値判定・振動波形解析など。
6. メンテナンス計画への反映
データにもとづき交換時期を最適化。
関連記事
関連書籍
まとめ
予知保全は、センサを使って設備の状態を監視し、故障の予兆を早期に発見してメンテナンスを行う保全方式です。
- 振動・温度・電流は最も重要な監視項目
- 突発停止を減らし、保全コストを最適化できる
- IoTセンサとクラウドを組み合わせれば導入しやすい
工場の安定稼働と省エネ・安全性向上のため、予知保全は今後さらに重要になる技術です。