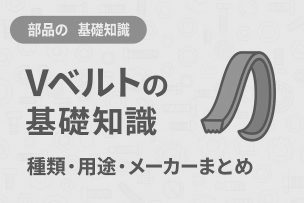静電気(Static electricity)とは、物体表面に電荷がたまることで発生する現象です。
冬場に金属へ触れたときの「バチッ」という放電が有名ですが、工場設備ではもっと深刻な問題を引き起こす場合があります。
この記事では、静電気の発生原理、放電の仕組み、設備トラブル例、対策方法をわかりやすく解説します。
静電気とは?
静電気は、物体同士が接触・摩擦したり、離れたりする際に電荷が偏ることで発生します。
電荷が溜まり、一定量を超えると空気中に放電し、火花やノイズを発生させます。
主な発生要因
- 摩擦(ベルト、ローラ、樹脂製ワーク)
- 剥離(フィルム、紙、シート)
- 乾燥した空気(湿度低下)
- 絶縁体の帯電(樹脂・フィルム類)
静電気の発生原理
静電気は、以下の3つのプロセスで発生します。
① 接触帯電
異なる物質が触れた瞬間、電子が移動して帯電する。
② 摩擦帯電
摩擦によって電子移動が増え、帯電量が大きくなる。
③ 剥離帯電
フィルムや紙を剥がすときに大量の電荷が発生する。
静電気が設備に与える悪影響
① センサー誤動作
放電ノイズにより、光電センサー・近接センサーが誤検知することがある。
② インバータ・PLCのノイズトラブル
静電気放電(ESD)がノイズ源となり、制御盤内の電子機器に影響。
③ 製品不良
フィルム・粉体・シートが静電気で張り付く、異物付着などの問題。
④ 火花による引火
溶剤環境・粉じん環境では特に危険。
⑤ 人体へのショック
オペレーターの作業性悪化、誤動作につながることもある。
静電気対策の基本
① 接地(アース)
静電気を地面へ逃がす最も重要な対策。
② 湿度管理
湿度40〜60%を維持すると帯電しにくい。
③ 除電器の使用(イオナイザ)
静電気中和に最も有効。
④ 帯電しにくい素材の使用
帯電防止フィルム・摩耗粉の少ない樹脂など。
⑤ シールド・ノイズ対策
制御盤・インバータ周りで重要。
現場で多いトラブル事例
- 搬送ラインのフィルムが貼り付く → 除電バー導入で改善
- 粉体がホッパー壁に付着 → 帯電防止剤が有効
- 近接センサーが誤動作 → アース改善+ルーティング見直し
- PLCが誤停止 → 静電気放電のノイズ影響
関連記事
関連書籍
まとめ
静電気は、製品不良・ノイズ・誤動作・引火など、工場設備に大きな影響を与える要因です。
- 摩擦・剥離・乾燥などで帯電が発生
- 静電気放電は電子機器やセンサーに悪影響
- アース・湿度管理・除電器が基本対策
適切な静電気対策を行うことで、設備の安定稼働と品質向上につながります。