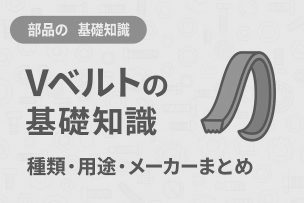PID制御(Proportional-Integral-Derivative control)は、工場設備・FA装置・プロセス制御でもっとも広く使われている自動制御方式です。
温度・圧力・速度・流量・位置など、多くの物理量を安定して制御できるため、産業オートメーションの基盤となっています。
この記事では、PID制御の仕組み、P・I・D の役割、調整方法、工場設備での具体的な使い方をわかりやすく解説します。
PID制御とは?
PID制御は、目標値(設定値)と実際の値(PV)の誤差をもとに、以下の3要素を組み合わせて制御量を決める方式です。
- P:比例(誤差に比例して制御)
- I:積分(誤差を時間で累積)
- D:微分(変化の勢いに応じて制御)
3つをバランス良く使うことで、応答の速さ・安定性・精度を両立します。
P・I・D 各要素の役割
P(比例)制御
誤差が大きいほど強く制御。
ただし、P だけではオフセット(残差)が消えない。
I(積分)制御
誤差を時間で累積し、ゼロに近づける。
設定値への追従性が向上。
ただし、入れすぎると振動する。
D(微分)制御
変化の勢いを抑えて安定させる。
ノイズで暴れやすいため使用量に注意。
PID制御の式(イメージ)
操作量 = P × 誤差 + I × 誤差の積分 + D × 誤差の微分
これにより、現在・過去・未来の振る舞いを予測しながら制御します。
PID制御が使われる工場設備
- 温度コントローラ(ヒータ制御)
- インバータの速度制御
- サーボモータの位置制御
- エアシリンダの圧力制御
- 流量・圧力のプロセス制御
産業機械のほぼすべてで活用されています。
PID調整(チューニング)の基本
- Pを上げる:応答が早くなるが振動しやすい
- Iを上げる:誤差が消えるが動作が重くなる
- Dを上げる:振動を抑えるがノイズに弱い
実務では「P → I → D」の順で調整するのが一般的です。
PID制御がうまくいかない原因
- 負荷変動が大きすぎる
- センサー精度が低い/ノイズが多い
- D要素が強すぎて振動が増大
- 制御対象が非線形
その場合は、
- フィードフォワード
- モデル予測制御(MPC)
などの高度制御が使われることもあります。
関連記事
関連書籍
まとめ
PID制御は、産業設備を安定して制御するための基本技術です。
- P・I・Dを組み合わせて誤差を抑える
- 温度・流量・速度・位置制御で広く利用
- 設定は P → I → D の順で行うのが基本
- 工場の品質・生産性に直結する重要技術
PID制御の理解は、あらゆる施設・自動機の最適運用に不可欠です。