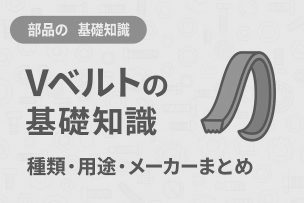点検や保守を正確に実施しても、その内容を「記録・報告」しなければ、改善や再発防止にはつながりません。
本記事では、点検記録・報告書の作成方法、記載すべき項目、デジタル化の進め方などをわかりやすく解説します。
現場で使える実践的なテンプレート作成のコツも紹介します。
点検記録・報告書の目的
点検記録は「実施した証拠」としての意味だけでなく、次回点検やトラブル発生時の原因分析、改善計画に活用できる重要なデータです。
設備の状態を時系列で把握し、劣化や異常傾向を早期に発見することが目的です。
記録を残すことで得られるメリット
- 点検漏れ・重複作業を防止できる
- 設備の異常傾向を分析できる
- 保守履歴として信頼性を証明できる
- 改善・更新判断の根拠となる
- 外部監査やISO・法令対応に有効
点検記録書・報告書の基本構成
点検記録書(チェックシート)は、現場担当者が使用する一次記録表。
点検報告書は、結果をまとめて上長や関係部門へ提出する二次資料です。
主な記載項目
- 設備名・管理番号・設置場所
- 点検日・点検者名
- 点検項目・基準値・測定値・判定結果
- 異常内容・発生箇所・原因・処置内容
- 今後の対応(再点検・部品交換・改善提案など)
- 写真添付・署名欄
チェックシート例(抜粋)
| 項目 | 基準値 | 測定値 | 判定 | 処置 |
|---|---|---|---|---|
| モーター絶縁抵抗 | ≧1.0 MΩ | 1.2 MΩ | ○ | 良好 |
| 冷却ファン動作 | 正常回転 | 問題なし | ○ | – |
| 異音・振動 | なし | 軽微 | △ | 再点検予定 |
報告書作成のポイント
① 「誰が・何を・いつ・どうした」を明確に
報告書は、後から第三者が見ても内容を正確に理解できるようにする必要があります。
5W1H(When・Where・What・Who・Why・How)を意識して簡潔にまとめましょう。
② 数値・写真を活用する
数値データや撮影画像を添付することで、客観性が高まり信頼性が向上します。
温度・振動・圧力などは定期的に測定し、グラフ化すると効果的です。
③ 異常の「原因」と「処置」を必ず記録
単に「異常あり」と書くだけでは不十分です。
「どの箇所が」「なぜ」異常になったのか、「どう対処したか」を明確に記載します。
④ 改善提案・今後の対応を追記
再発防止策や今後の点検計画を記載しておくと、上長や設備管理者が判断しやすくなります。
⑤ 記録フォーマットを統一する
部署・担当者ごとにフォーマットが異なると比較や集計が困難になります。
共通テンプレートを設定し、電子化・クラウド共有を進めましょう。
デジタル化・クラウド管理のすすめ
最近では、タブレットやスマートフォンで入力できる「デジタル点検システム」が普及しています。
紙の記録と比べて、検索・共有・分析が容易になり、管理効率が向上します。
主なメリット
- 記録ミス・転記漏れを削減
- リアルタイムで報告・承認が可能
- 過去データの検索・グラフ化が容易
- 異常検知や警告を自動通知
おすすめの点検・報告支援ツール
Q&A
Q. 点検記録はどのくらい保存する必要がありますか?
A. 法令上の保存期間は設備によりますが、一般的には3〜5年が目安です。
法定点検や品質保証に関わる記録は、7年以上保管するケースもあります。
Q. 写真付き報告書を効率的に作る方法はありますか?
A. タブレットで点検と同時に写真を撮影し、自動的にレポートへ添付できるアプリを活用すると効率的です。
Q. 点検報告書はExcelでも良いですか?
A. Excelは十分活用可能です。
共有や履歴管理を考える場合は、Googleスプレッドシートやクラウド管理への移行もおすすめです。