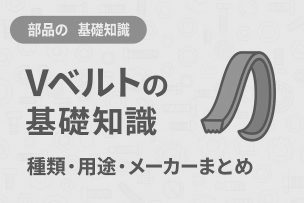工場設備や機械を長く安全に使い続けるためには、計画的な保守(メンテナンス)が欠かせません。
この記事では、設備保守の基本的な考え方と、点検スケジュールの立て方をわかりやすく解説します。
生産ラインの安定稼働やコスト削減のための基本知識としてご活用ください。
設備保守とは(基礎知識)
設備保守(メンテナンス)とは、機械・装置を良好な状態に保ち、性能を維持するための一連の活動を指します。
主な目的は、「故障の防止」「安全性の確保」「生産性の維持」「寿命の延長」です。
点検・清掃・給油・部品交換・記録管理などが保守の基本業務です。
設備保守の3つの柱
- 点検(Inspection): 設備の状態を確認する活動
- 整備(Servicing): 部品交換や清掃、給油などの軽整備
- 修理(Repair): 故障時の修復・部品更新
保守の目的と効果
- 突発的な故障・停止の防止
- 品質不良や安全事故の予防
- 設備の寿命延長・更新コスト削減
- 安定した生産能力の維持
- 省エネ運転・稼働効率の最適化
保守の種類
保守には大きく「予防保全」「事後保全」「予知保全」の3種類があります。
- 予防保全: 故障を未然に防ぐために計画的に実施する保守(例:定期点検・部品交換)
- 事後保全: 故障後に修理を行う保守(例:トラブル発生時の修復)
- 予知保全: センサーやデータ解析により、劣化を予測して行う保守(例:振動・温度監視)
点検スケジュールの立て方
設備の点検スケジュールは、「日常点検」「定期点検」「法定点検」の3段階で計画するのが基本です。
① 日常点検(Daily Check)
作業者が日々の運転前・運転中・運転後に行う簡易チェック。
異音・振動・油漏れ・温度・表示ランプなどを目視で確認します。
② 定期点検(Periodic Check)
専門担当者が一定周期で行う詳細点検。
機器内部の摩耗・劣化を確認し、グリース補充や部品交換を行います。
③ 法定点検(Legal Inspection)
法令で義務付けられている設備(ボイラー、圧力容器、受変電設備など)を対象に、定められた周期で実施します。
結果は記録・報告義務があります。
代表的な点検周期の目安
| 設備・機器 | 日常点検 | 定期点検 | 法定点検 |
|---|---|---|---|
| モーター・ポンプ | 毎日 | 3〜6か月 | 該当なし |
| コンプレッサ | 毎日 | 1〜3か月 | 圧縮機規模により該当 |
| ファン・ブロワ | 毎日 | 6か月 | 該当なし |
| 冷却塔(クーリングタワー) | 週1〜月1 | 6か月 | 該当なし |
| 受変電設備 | 運転監視 | 年1回 | 電気事業法により義務 |
| 空調・エアドライヤ | 毎日 | 3〜6か月 | 該当なし |
効果的な保守管理のポイント
- 点検結果を記録・データ化して傾向分析する
- 重要設備には予防保全・予知保全を導入
- 担当者間で点検基準・判断基準を共有
- IoTセンサーやクラウド管理を活用し効率化
- 点検履歴を基に最適な交換周期を見直す
おすすめの点検・保守ツール
Q&A
Q. 点検スケジュールはどのように作成すればよいですか?
A. 設備ごとに「重要度」「稼働時間」「法定要件」を基準に点検周期を決め、カレンダー形式で管理するのが効果的です。
Q. 設備が多く管理が大変です。効率化の方法はありますか?
A. IoTやクラウド管理ツールを活用することで、点検履歴や警告を自動で記録・共有できます。
Q. 点検表はどのように作れば良いですか?
A. 点検項目・基準値・判定欄を含むフォーマットをExcelで作成し、毎回記録する方法が一般的です。
最近では、テンプレートを使ったデジタル点検表も普及しています。