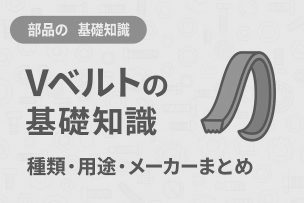設備保全の基本は「予防保全」と「事後保全」に大別されます。
どちらも設備の安定稼働を目的としていますが、実施のタイミングや考え方が異なります。
この記事では、それぞれの特徴やメリット・デメリット、実際の現場での使い分け方を詳しく解説します。
設備保全とは?
設備保全とは、機械や装置を安全かつ安定して稼働させるために、故障の防止・修理・更新などを計画的に行う活動を指します。
生産性を維持し、トラブルによる損失を最小限にすることが目的です。
主な保全の種類
- 事後保全(Corrective Maintenance): 故障や異常が発生してから修理する方式。
- 予防保全(Preventive Maintenance): 故障が起きる前に点検や部品交換を行う方式。
- 予知保全(Predictive Maintenance): データや診断技術を用いて劣化を予測する方式。
予防保全とは?
予防保全とは、設備が故障する前に点検・整備・部品交換などを行い、トラブルを未然に防ぐ手法です。
「壊れる前に対処する」アプローチであり、安定稼働や品質維持に直結します。
主な特徴
- 計画的に点検・整備を実施
- 故障リスクを事前に低減
- 生産ライン停止の防止
- 安全性・信頼性の向上
メリット
- 突発故障を大幅に削減
- 設備寿命を延ばせる
- 安定稼働率が向上
デメリット
- 点検・交換コストが発生する
- 問題がない部品を交換してしまう場合がある
- 停止時間の調整が必要
事後保全とは?
事後保全とは、設備が故障してから修理や部品交換を行う方式です。
「壊れたら直す」スタイルであり、初期コストは抑えられますが、停止による損失が大きくなることがあります。
主な特徴
- 故障や不具合発生後に対応
- 保守コストが発生するのは必要なときのみ
- 突発停止や生産ロスのリスクが高い
メリット
- 点検や部品交換の手間が少ない
- 稼働率を優先できる(停止が少ない)
- 低頻度設備や非重要設備に適用しやすい
デメリット
- 突発的な生産停止や納期遅延が起こりやすい
- 修理費用が高額化する可能性
- 安全リスク・品質リスクが高まる
予防保全と事後保全の比較
| 項目 | 予防保全 | 事後保全 |
|---|---|---|
| 実施タイミング | 故障前(定期・計画的) | 故障後(必要時のみ) |
| 目的 | 故障の未然防止 | 故障からの復旧 |
| コスト特性 | 定期的にコストが発生 | 突発的に高コスト化 |
| 稼働率 | 安定して高い | 不安定で停止リスクあり |
| 対象設備 | 重要設備・連続稼働ライン | 補助設備・低稼働機器 |
予知保全との違い
予知保全(Predictive Maintenance)は、IoTセンサーやAI解析を用いて設備の状態を監視し、故障の兆候をデータで把握して保全を行う方式です。
予防保全の発展形として注目されており、振動解析・温度監視・電流解析などが代表例です。
適切な保全方式の選び方
すべての設備に予防保全を導入するのはコスト過多となるため、重要度・稼働時間・故障リスクを基準に使い分けます。
- 重要度の高い設備:予防保全または予知保全
- 補助的設備・低稼働設備:事後保全
- 安全・品質に関わる機器:計画的な点検必須
保全活動を効率化するツール
Q&A
Q. 予防保全と事後保全のどちらを優先すべきですか?
A. 生産ラインや重要設備には予防保全を、補助的な設備には事後保全を組み合わせるのが一般的です。
Q. 保全コストを抑えるにはどうすればいいですか?
A. 状態監視センサーを用いた予知保全を導入することで、無駄な点検を減らし効率化が可能です。
Q. 保全方式は後から変更できますか?
A. はい。設備の稼働状況やトラブル頻度に応じて、事後保全から予防保全へ移行するケースが一般的です。