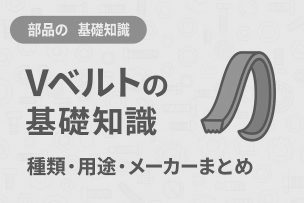モータや配電盤、ケーブルなどの電気設備では、絶縁劣化が進行すると漏電や焼損につながるおそれがあります。
この記事では、絶縁抵抗測定を活用した「電気絶縁診断」の基本と、劣化傾向を早期に見抜くポイントを解説します。
電気絶縁診断とは?(基礎知識)
電気絶縁診断とは、モータやケーブル、変圧器などの絶縁状態を数値化して評価する点検手法です。
絶縁が劣化すると漏電や地絡のリスクが高まるため、定期的な診断が欠かせません。
- 絶縁抵抗値を測定して健全性を評価
- 経年変化から劣化傾向を分析
- 異常値の検出により早期修理・交換を判断
絶縁劣化の主な原因
絶縁性能は、経年だけでなく環境要因や運転条件によっても低下します。
| 要因 | 具体例 | 対策 |
|---|---|---|
| 熱 | モータの過負荷・冷却不良による温度上昇 | 冷却経路清掃、負荷調整 |
| 湿気 | 屋外盤・配線内の結露、湿潤環境 | 乾燥処理、除湿器・ヒータ設置 |
| 汚損 | 粉塵・油分によるトラッキング | 定期清掃、防塵・防油カバー設置 |
| 機械的ストレス | 振動・引っ張り・曲げによるケーブル損傷 | 固定具の改善、ケーブル保護材使用 |
| 経年劣化 | 絶縁材料の硬化・ひび割れ | 定期交換、補修絶縁材の使用 |
絶縁診断の基本手法
絶縁抵抗計(メガー)を用いた測定が基本です。対象の種類や電圧階級に応じて、測定電圧と判定基準を選定します。
| 対象設備 | 測定電圧 | 良否判定の目安 |
|---|---|---|
| 低圧モータ(AC200V) | 500V | 1MΩ以上が望ましい |
| 高圧モータ(AC3.3kV) | 1000〜2500V | 100MΩ以上が目安 |
| 配電盤・制御盤 | 500〜1000V | 配線系統ごとの比較で評価 |
| ケーブル(CV・VCTなど) | 1000V以上 | 1MΩ/km以上を確保 |
測定から診断までの流れ
- 対象設備の電源を遮断し、安全確認を実施
- 接続端子を開放し、測定電圧を設定
- 絶縁抵抗を測定(各相—接地間など)
- 測定結果を前回値と比較して変化を確認
- 経時変化をグラフ化し、劣化傾向を分析
単一の数値で判断するのではなく、「過去との比較」「温度補正」「乾燥状態の影響」を考慮することが重要です。
診断結果の読み取りと対策
| 結果の特徴 | 想定される状態 | 対応策 |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗値が徐々に低下 | 経年劣化・湿気の影響 | 乾燥処理・交換検討 |
| 急激な低下を確認 | ケーブル損傷・接続部破損 | 該当箇所の絶縁補修 |
| 測定値にばらつきが大きい | 汚損・端子ゆるみ | 清掃・端子再締結 |
| 測定時に不安定な波形 | 湿潤状態・トラッキング初期 | 絶縁乾燥処理を実施 |
長期劣化の傾向管理
絶縁診断は「定期測定データの推移」を追うことで精度が高まります。
月次・年次点検での数値比較やグラフ化により、異常傾向を早期に把握できます。
- 設備ごとの基準値を設定し、異常検知を自動化
- クラウド管理ツールによる記録・傾向管理
- 異常値の通知アラート設定
代表的な絶縁診断機器
| メーカー | 主な製品・特徴 |
|---|---|
| 日置電機(HIOKI) | デジタル絶縁抵抗計。データ記録機能付きモデル多数。 |
| 三和電気計器(SANWA) | 携帯型メガー。現場保守用として定番。 |
| 横河電機(YOKOGAWA) | 高精度測定対応。研究・生産ラインでも使用。 |
| キーエンス(KEYENCE) | 設備監視システムと連携できるオンライン絶縁診断機。 |
まとめ
電気絶縁診断は、モータやケーブルの健全性を守る重要な保全業務です。
定期測定による劣化傾向の可視化と、異常発生時の早期対応により、設備の信頼性と稼働率を維持できます。
関連記事
- 絶縁抵抗計の測定と管理ポイント
- 赤外線サーモグラフィ診断の基礎|温度分布でわかる劣化・異常箇所
- 超音波探傷・漏れ検査の基礎|目に見えない欠陥・漏れを検出する技術
- 振動診断の基礎と実践|異常波形から原因を特定する方法