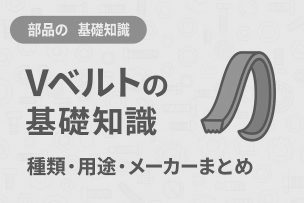モーター・配電盤・配管・ベアリング・食品・空調ダクトなど、現場には「温度監視が必要なポイント」が数多く存在します。
そこで活躍するのが温度計と赤外線サーモメーター(非接触温度計)です。
本記事では、接触式/非接触式の違い・選び方・使い方・注意点を、設備保全・整備・DIYユーザー向けにわかりやすく解説します。
温度計・赤外線サーモメーターとは?
温度測定用の計器は大きく分けて、対象物に触れて測る接触式温度計と、離れた場所から測れる非接触(赤外線)温度計の2種類があります。
接触式温度計
- 熱電対式: 広い温度範囲を測定可能。工業用で定番。
- サーミスタ式: 高感度で精度が高く、−50〜+150℃程度の範囲に強い。
- 表面温度プローブ: 配管・ベアリングなどの表面温度測定に。
非接触(赤外線)温度計
対象物から放射される赤外線エネルギーを検出し、その強さから温度を算出します。
メリット: 高温・回転体・危険箇所など、触れない場所を安全に測定できることが最大の魅力です。
用途別の使い分け
| 用途 | 向いている測定器 | 理由 |
|---|---|---|
| 配電盤・ブレーカ・端子台 | 赤外線温度計 | 通電中でも安全に測定可能。 |
| モーター・ベアリング温度 | 赤外線温度計+接触式 | 異常発熱の確認と詳細測定。 |
| 食品・厨房・冷蔵庫 | 防水接触式温度計 | 食中毒対策の中心は「中心温度」。 |
| 空調ダクト・吹き出し口 | 赤外線温度計 | 高所・届きにくい場所でも測定可。 |
赤外線温度計の選び方
① 測定温度範囲
- 一般設備・空調用途:−50〜+500℃程度で十分。
- 炉・溶接・鋳造ライン:〜800℃以上の高温対応モデルが必要。
② 距離対スポット比(D:S)
「どれくらい離れた距離から、どの範囲を測るか」を示す指標です(例:12:1なら、12cm離れた位置で直径1cmの範囲を測定)。
- 近距離でピンポイント測定が多い → 8:1〜12:1程度
- 離れた場所から測りたい → 20:1以上のモデル
③ 放射率設定
金属・塗装面・樹脂など、素材によって放射率(表面から放出される赤外線の割合)が異なります。
放射率可変モデルを選ぶと、測定対象に合わせて補正ができ、精度が向上します。
④ 防塵・防水・耐環境性能
- 工場・屋外で使用 → IP54以上の防塵防滴モデルが安心。
- 油・粉塵が多い場所 → レンズ保護キャップ付きがおすすめ。
おすすめの温度計・赤外線サーモメーター
| 製品名 | 特徴 | 購入リンク |
|---|---|---|
| HIOKI FT3700-20(赤外線温度計) | −60〜+550℃対応。現場向けの定番モデル。 | Amazon| 楽天 |
| テストー 830-T2(赤外線温度計) | 距離対スポット比12:1。工場・空調・食品まで幅広く対応。 | Amazon| 楽天 |
| シンワ測定 デジタル温度計 T型センサー付 | 接触式プローブ付き。配管・表面温度測定に最適。 | Amazon| 楽天 |
| タニタ デジタル温度計 TT-533 | 食品・厨房向け。防水仕様で衛生管理に使いやすい。 | Amazon| 楽天 |
正しい使い方と注意点
非接触(赤外線)温度計のコツ
- 測定距離を守る: 距離対スポット比を超えると周囲の温度も混ざって誤差が増える。
- 光沢面は注意: 鏡面仕上げの金属は反射が強く、表示温度が低めに出やすい(テープを貼るなどして補正)。
- レンズをきれいに: ほこり・油膜は測定誤差の原因。
接触式温度計のポイント
- センサーをしっかり密着させる。
- 十分な時間をおいて温度が安定してから読む。
- 食品用途では防水・防滴・洗浄しやすい構造を選ぶ。
体表面温度測定について
工業用の赤外線温度計は、「人の体温測定」には原則として非推奨です。
医療用として認証された体温計とは設計思想が異なり、誤差が大きくなります。
人の発熱チェックには必ず医療用体温計・非接触体温計を使用しましょう。
メンテナンスと校正
- 年1回を目安に、基準温度との差を確認。
- 極端な高温環境・直射日光下への放置は避ける。
- 電池残量が少ないと誤表示の原因になるため早めに交換。
関連記事
まとめ
温度計・赤外線サーモメーターは、設備の異常発熱や食品の安全管理を「見える化」する重要なツールです。
接触式と非接触式の特徴を理解し、用途に合った温度範囲・距離対スポット比・防塵防水性能を持つモデルを選ぶことで、現場の安全性と効率を大きく高めることができます。