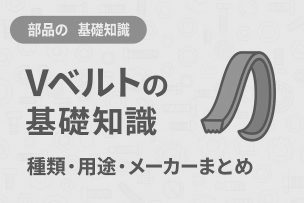電気料金の明細を見ると「kW」と「kWh」が並んでいますが、この2つの違いを正確に説明できる人は意外と多くありません。
設備の省エネや電気料金削減を考えるうえでは、電力(kW)と電力量(kWh)の違いを理解しておくことが重要です。
この記事では、kWとkWhの意味、計算方法、電気料金との関係を、工場・設備の実務目線でわかりやすく解説します。
電力(kW)とは?
電力(kW)は、「どれだけの速さで電気エネルギーを使っているか」=使用している瞬間のパワーを表します。
- 1kW = 1000W
- モーターの定格出力、ヒーター容量、契約電力 などで使われる
- 「今この瞬間にどれだけ使っているか」を示す量
例:
- 3kWのヒーター → 最大で3kWの電力を消費する
- 5.5kWモーター → 定格運転で約5.5kWの電力を必要とする
電力量(kWh)とは?
電力量(kWh)は、「どれだけの時間、電力を使ったか」を掛け合わせた“電気エネルギーの総量”です。
基本式は次のとおりです。
電力量(kWh)= 電力(kW) × 使用時間(h)
例:
- 3kWのヒーターを2時間使う → 3 × 2 = 6kWh
- 5.5kWモーターを4時間運転 → 5.5 × 4 = 22kWh
電気料金は基本的に「kWh単価 × 電力量(kWh)」で計算されるため、請求書で金額に直結するのは「kWh」の方です。
kWとkWhの違いをイメージで理解する
よく使われる例えは「自動車の走行」です。
- kW(電力) → エンジンの“馬力”=瞬間的なパワー
- kWh(電力量) → 走った“距離”に相当するエネルギー消費量
同じ10kWhを使ったとしても、
- 1kWを10時間使う = 10kWh
- 2kWを5時間使う = 10kWh
となり、どちらも電力量は同じです(電気料金も同じイメージ)。
工場・設備でよくある誤解
- 「モーターのkWが大きい=電気代が高い」と考えがちだが、実際には使用時間も重要
- 待機中の設備でも、制御電源や待機電力が積み重なると、kWhとしては無視できない
- 「契約電力(kW)」と「使用電力量(kWh)」は別物
契約電力は「最大どれだけ同時に使うか」、電力量は「トータルでどれくらい使ったか」を表します。
電力量(kWh)の具体的な計算例
例1:コンプレッサ1台の場合
- 定格電動機:22kW
- 平均負荷率:70%(0.7)
- 運転時間:1日8時間 × 20日 = 160時間
この場合の電力量は、
22kW × 0.7 × 160h = 2464kWh
となります。
例2:照明設備の場合
- LED照明:0.1kW(100W) × 50台 = 5kW
- 点灯時間:1日10時間 × 22日 = 220時間
5kW × 220h = 1100kWh
たとえ1台あたりの電力が小さくても、台数と時間が掛け算されると、
電力量(=電気代)としては大きなインパクトになります。
電気料金とkW・kWhの関係
一般的な高圧電力契約では、次のような料金構成になります。
- 基本料金: 契約電力(kW)に比例
- 電力量料金: 使用電力量(kWh)に比例
- その他:再エネ賦課金、力率割増・割引 など
省エネ対策としては、
- 最大需要電力(kW)を下げて基本料金を削減
- 運転時間・無駄な待機を減らして電力量(kWh)を削減
の両面から考える必要があります。
関連記事
- エネルギーマネージメントシステム(EMS)とは。EMSと関連用語
- 電流センサ・電力センサの種類と選び方
- データロガー(温度・電力・環境)の基礎知識
- エネルギー可視化クラウドの活用法
- 電力量計・エネルギーモニタの基礎知識
関連書籍
まとめ
電力(kW)と電力量(kWh)は、似ているようで役割が異なります。
- kW: 今どれだけの電気を使っているか(瞬間のパワー)
- kWh: どれだけの時間使ったかを掛け合わせた“電気の総量”
- 電気料金は主にkWhに比例し、基本料金はkW(契約電力)に比例
設備の電気使用状況を正しく把握するには、「kWを下げる」「kWhを減らす」の両面で考えることが重要です。